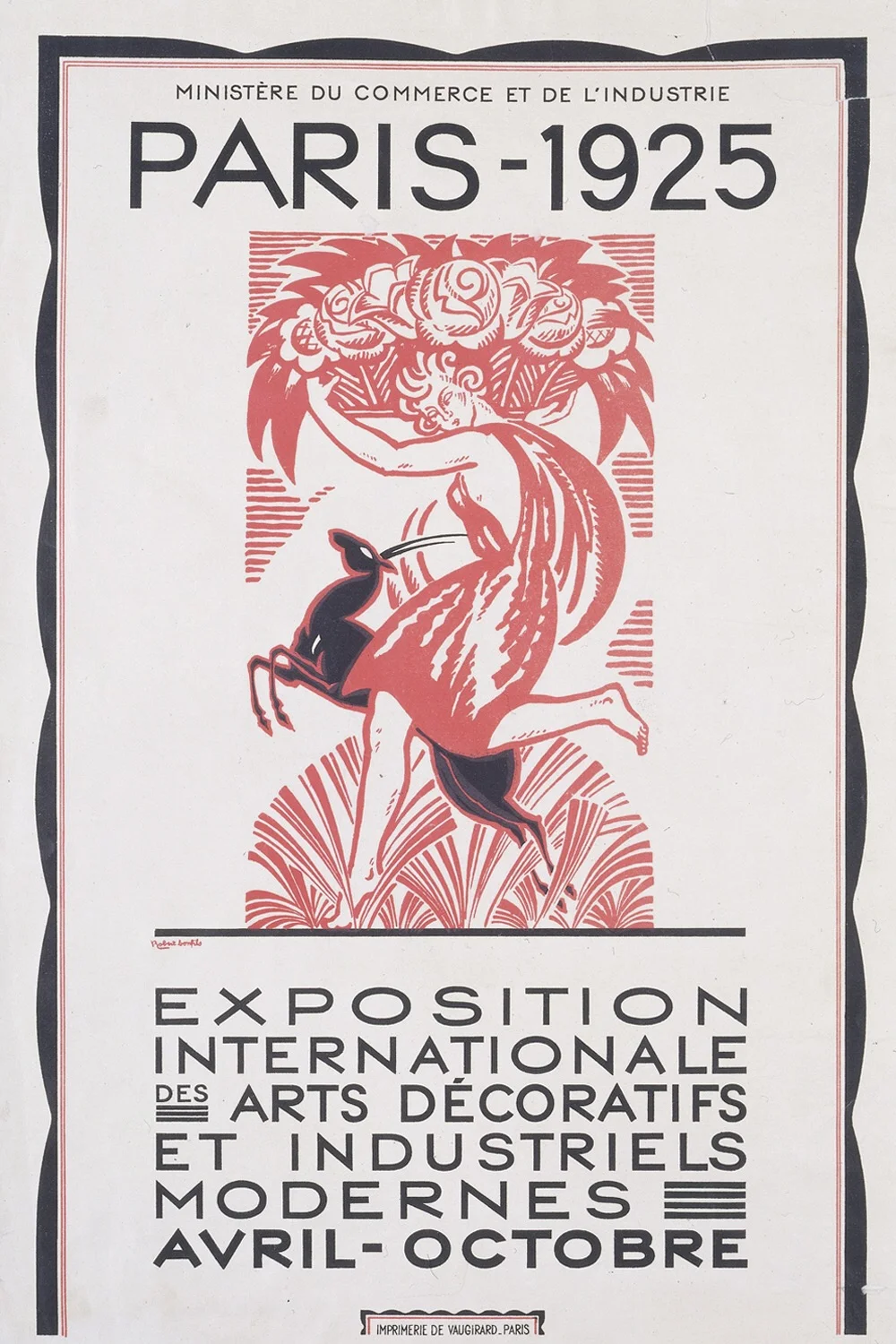皆さんこんにちは。MATSUです。 いきなりだけど、映画は素晴らしいコンテンツで教科書だ。
新旧問わず掘り下げながらいろいろ見るようにしていて、その映画の時代背景、ファッションスタイル、アイウェアまで映像に記録されているリアリティは大変興味深いものです。分厚い小説を短時間で1冊読めたらそれが1番良いけど、映画は2時間程度の映像に凝縮されているから、目で見ていても耳で聞いていてもいろいろな事が発見できます。
内容だけではなく"サウンド・トラック"(映画音楽)もその映画用に当時のミュージシャンが楽曲を録音していて、めちゃくちゃカッコいいレコードもたくさんあって同時に楽しめちゃいます。
特にその中でも昔あまり評価されなかったB級映画などの"カルト・ムービー"の音や映画の内容がヤバかったりします。(僕自身、カルト・ムービーのオタクです)
映画には"時代設定"があり、その時代のキャラクターに合わせたメガネやサングラス、ハットなど小物類も登場してくるものもあるので、観察して見ているとその時代のトレンドは一貫しているものがあり、学ぶ事ができます。
皆さんも知っている身近な映画からも見る事ができます。
Superman(1951)
1994年公開の映画"Quiz Show"では1950年代を舞台にした実話の映画で、実在した伝説の人気クイズ番組を描いた作品。そこに登場する挑戦者の男は50年代のタート・アーネルをかけていたり、普段着は50sファッションだったりとちゃんと時代設定に基いています。
1950年代はウェリントン型のセル・フレームがマスト・アイテム。Quiz Show(1994)
ブラピ主演の"Benjamin Button"は、1918年代戦後に"生まれてから若返っていく"という奇妙な話で設定が少しだけ曖昧だけど、同じく50年代のタート・アーネルをかけていたり、ブリム(ツバ)の広いハットをかぶっているという事は50年代という設定でしょう。
50年代のスーパーマンの風貌とそっくりです。Benjamin Button(2008)
ニコラス・ケイジ主演の"Face Off"では、キレキレのギャング役を演じていて、ギャングのイメージらしい赤いレンズの"リム・レス"(2ポイント)のドロップ・オクタゴンをかけています。時代設定は現代っぽいですが、ちゃんと30年代頃のギャングスター像を再現しています。
Face off(1997)
それに関連して、1930年代から1940年代にかけて活動したジャズの巨匠でもあり"ビバップの父"と呼ばれたチャーリー・パーカーも、イケイケの全盛期はギャング顔負けの出で立ちで全く同じ形のドロップ・オクタゴンをかけています。同じく深い赤茶色系の色を入れてワルさが倍増。
チャーリー・パーカーなどこの時期のジャズマンは、ギャングばりのワルも多かったからスタイルが一貫して似ています。1930年代に活躍したギタリストのチャーリー・クリスチャンもかけてますね◎
1930年代のミュージシャンやギャング、ちょっと普通じゃないリベラルな人たちにはドロップ・オクタゴンがマスト・アイテムだったという事がうかがえます。
1930年代に実在した伝説の強盗ギャングを描いた"Public Enemy"でジョニー・デップは、見事にギャングらしい"パイロット・フルビュー"に赤いレンズを入れてかけています。
やはりニコラス・ケイジやチャーリー・パーカー同様に"赤いレンズ"="ギャング"は危ないカラーレンズのイメージを強めてくれるみたいですね。
Public Enemy(2009)
時代設定のファッションには過去から現代まで一貫して共通している事が分かります。
皆さんもこれから映画を見る時は時代設定や、その時代のファッションをちょっと気にして観察してみたら発見があって楽しいですよ◎
それでは次回もお楽しみに。サヨナラ、サヨナラ、サヨナラ(淀川長治風)
SOLAKZADE
MATSU
![SOLAKZADE®︎ソラックザーデ [ヴィンテージ&ビスポーク ジュエリー・眼鏡・時計・車]](http://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5b0a9011f7939242735d024f/1603535978383-XIRO0BQ1PDZ03TEFBEZT/logo.web2020.10.png?format=1500w)